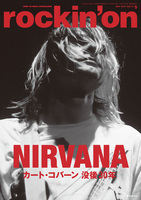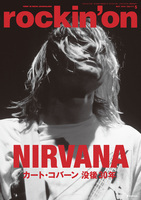多くの人が感想を述べている通り、原作が素晴らしく、片渕須直監督の手腕も見事で、のんの声の演技も素晴らしい。コトリンゴの音楽も本当に素晴らしい。
僕は片渕監督の映画を初めて観たのだが、ポスト宮崎駿世代のアニメーション監督の第一人者として圧倒的な力量と独自性を感じた。
主人公すずが「ぼうっとしている」というのがこの映画の最も革新的なところだ。
すず自身がセリフとして何度も言っているように、すずは「ぼうっとしている」。
第二次世界大戦中の広島県呉市、という緊迫した時期を描いたアニメーションで、戦争、原爆、死を真正面から描いた作品であるが、その主人公であるすずは「ぼうっとしている」。
初恋の瞬間にも、他所へ嫁に行くときにも、空襲の中を必死で生き延びる間も、自分の右手を失い、姪っ子を失うときも、原爆が落ちたときも、すずは「ぼうっとしている」。
空襲のシーンでは「いま絵の具と筆があれば…」とか考えているし、姪っ子を失うときも妄想の中を彷徨ってしまっている。
そこが、宮崎駿監督の主人公とはまったく違うところだ。
ナウシカもキキもアシタカもサンも千尋も、ぼうっとはしていない。
誰よりも覚醒し、すごいスピードで駆け抜け、驚くべき速さで成長していく。
物語の瞬間に真正面から向き合い、その出来事の意味を誰よりも早く自己同一化して次のシーンへと躍り出ていく。
だが片渕監督が描くすずは違う。どんな出来事が目の前に起きても、それが何なのかがわからずに「ぼうっとしている」。
そして後からそれを拾い集めるようにして少しづつ理解していく。
その理解の歩調に合わせるように、そこからゆっくりと丁寧に生きようとする。
のんの声の演技はそれを実に的確に表現している。
そしてすずだけではなく、このアニメの登場人物たちはみな、そういうふうに生きていて、その生き方がこの映画の物語の本質になっているのだ。
1941年生まれの宮崎監督と1960年生まれの片渕監督の、世代による違いもあるのかもしれないと思う。
僕は62年生まれなので片渕監督に近くて、この何があってもリアルに感じられずにぼうっとしてしまう感覚は非常によくわかる。
上の世代の人がはっきりとした意見を持ち、瞬時に物事を判断して、すぐに行動を起こせるのが不思議で、そんな姿を見ながら横でポカーンとしてしまうことが今でもよくある。
音楽の世界でも、清志郎や桑田さんや矢沢さんや浜田省吾さんの、あの常にリアルで覚醒していて力強い感じは、それよりも下の世代とは明らかに一線を画している。
話が逸れた。
僕はぼうっとしていても覚醒していてもどちらでもいいと思う。
生きるということにおいてそれらの間に価値の優劣などない。
ただ、戦争を描いたアニメーションにおいて、「ぼうっとしている」すずを見事に主人公として描いたこの作品の意味はとても大きいと思う。
ぼうっとしてしまう人間を疎外しない物語。
ぼうっとしてしまう人間をむしろ主人公にした物語。
しかも「戦争」という状況の中で。
まるで1997年にベックが”loser”で登場した時のように、なんだかやたらと救われた気がしたのだ。